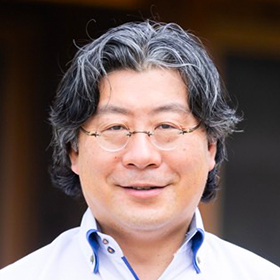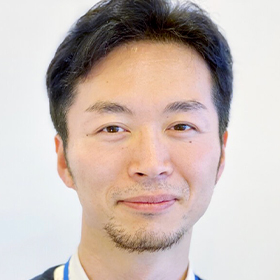災害時、すぐに現地に向かうことは難しい。
けれど、被災地の医療や日常を守る方法は他にもあります。
「間接災害支援」という形で、
現地にいる医療者をサポートする仕組みに、あなたも参加しませんか?
間接的な支援が、被災地や周辺地域の日常を支えることができ、
また現地の医療者にとっての大きな力になります。
新たな支援者として、あなたの登録をお待ちしています。
お知らせ
-
2025.06.15第7回日本在宅医療連合学会大会 シンポジウムを開催いたしました。
-
2025.06.10登録フォームをオープンしました。
-
2025.06.10ホームページを公開しました。
HoMATとは?
一般的な「直接災害支援」では、外部の医療者が被災地に入り支援を行いますが、現場の混乱や支援の継続性に課題があります。
被災地では、入れ替わり訪れる医療者により、被災者の方は同様のアンケートが繰り返される「アンケート疲れ」や、情報の重複、支援方針の違いによる混乱が生じやすくなります。受け入れ側の医療者にも、毎回のオリエンテーションや支援者間の調整による精神的・時間的な負担がかかっています。
こうした課題を解決するために、「間接災害支援」という新しい支援の形を構築しました。
HoMATの特徴
-
“現地”の医療者が、“被災地”に長期的に滞在できる体制を支援
「HoMAT派遣医療者」は、災害対応医療者が地元で行う通常診療を代診します。これにより現地の情報に詳しい、現地や周辺地域の医療者が安心して長期的に災害対応に専念できるようなバックアップ体制をつくります。
-
日頃から在宅医療に携わる医療者が支援
日頃から地域に密着し、個別性の高いケアに対応している在宅医療の医療者だからこそ、柔軟に対応できます。
-
全国にネットワークを広げ、様々な状況でも対応可能な体制を構築
広域でのネットワーク連携により、被災の影響を受けにくい地域同士が支援できる体制を構築します(例:北海道と九州、日本海側と太平洋側)。
平時からネットワークを築き、災害時には迅速に対応できるよう、定期的な訪問・交流・段取りの確認を行っていきます。
HoMATの経緯
-
2021年8月
菅首相(当時)に、有志代表 市橋・佐々木が、HoMATの初期アイディアをプレゼンテーション。
-
2023年5月
公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団「在宅医療推進のための研究」に採択。
研究テーマ:『大規模災害時の在宅医療機関相互協力~広域 BCP 活動に必要な支援体制構築の研究~』 -
2023年10月
全国の在宅医療関係者に声をかけ、zoom会議への参画を促す。
-
2023年11月22日
第一回zoom会議始動。HoMATの理念について説明、登録者のネットワークづくりを行った。
-
2023年12月
「HoMAT」slack オープン。
-
2024年1月1日
令和6年能登半島地震発生、同日slackにて情報共有開始。
- 毎週zoom会議を実施、情報交換。
-
2024年1月5日
間接災害支援を決定。
-
2024年8月4日
第二回zoom会議開催。能登半島地震でのHoMAT出動 間接災害支援の振り返りを行った。
-
2024年11月24日
第三回zoom会議開催。他地域支援シュミレーション研修事業の事前打合せ、学会報告について行った。
-
2025年2月
他地域支援シュミレーション研修実施
-
2025年6月
第7回日本在宅医療連合学会大会 シンポジウムを開催。
YouTube
Podcast
GoogleNotebookLMによる、AI生成のPodcastです。漢字の読み方の間違いは、ご容赦ください。
参加者の声
活動実績
令和6年1月の能登地震での支援の出動実績レポートです。具体的な出動内容、活動実績評価をまとめています。

登録フォーム
ご支援・ご寄付
よくあるご質問
登録をご検討の方
登録をした人は、必ず出動しなければいけませんか?
- 登録後は必ず出動しなければならないわけではありません。
- 登録者のスケジュールを確認し、受け入れ先の事業所と連携しながら決定します。
- 予定は柔軟に調整が可能です。確定後に出動が難しくなった場合も、バックアップできますので、ご連絡ください。
- 出動医療機関は、被災地の場合もあれば、そうでない場合もございます。
出動の際に、事前に準備するものはありますか?
出動が決定次第、下記の免許証・資格証のデータ送付をお願いいたします。
- 医師の場合:医師免許証・保険医登録証のデータ送付
- その他の専門職の場合:資格証のデータ送付
- 振込口座
出動の際は、受け入れ先の非常勤として登録される形となります。保険は、受け入れる医療機関がかけているものを利用します。
出動の際に、何を持参する必要がありますか?
聴診器、印鑑(シャチハタ可)、必要な場合に対応できる靴(雪の日などは長靴)をご持参ください。
その他の必要なものにつきましては、出動で受け入れ先の事務局にお問合せください。
HoMAT登録者の連絡手段は、何ですか?
平時は、メールで連絡いたします。災害発生時は、slackで情報交換します。
出動の際は、費用はどこが負担しますか?
原則的には、受け入れ先の事業所が負担となります。交通費や宿泊費は寄付金から調達できるようにしていきたいと考えております。
HoMAT登録後の流れを教えてください。
HoMAT登録が完了しましたら、事務局側にてHoMAT登録者リストに追加いたします。災害発生時には、新たにSlackグループを立ち上げ、そちらで情報交換を行います。無理のない範囲でご参加ください。
支援受け入れをご検討の方
災害時、HoMATの支援を受けたい場合は、どのようにしたら良いですか?
HoMAT登録者は、まずは事務局に連絡をお願いいたします。
あらかじめHoMATに登録をしていない場合でも、支援の依頼は可能ですか?
事前の登録は必要ありません。まずは、災害発生時にご相談ください。HoMAT登録者(支援者)を送ることが可能な場合、支援します。必ず支援者を送ることができるかは、サポートの人数の集まり次第になるため、状況次第では分かりかねます。その時のできる限りの最善を尽くしたいと考えています。
登録施設として、事前に準備しておかないといけないことはありますか?
可能でしたら、宿泊の場所を確保していただきたいです。難しい場合は、近隣のホテルの紹介など、アレンジしていただけますと有難いです。